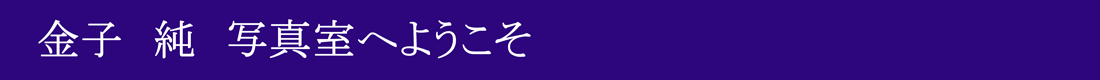ヒエラポリスから湧き出るカルサイト(方解石)を含む温水が、 石灰岩でできた岩肌を流れる時に二酸化炭素が発生し、 炭酸カルシウム塩となって凝結し、 年月の経過と共に石化した滝になりました。 |
 ユネスコの世界遺産に登録されているパムッカレは 綿の城という意味の名前を持ち、 真っ白な湧泉沈殿物が岩肌を覆い、 まるでお城のような構えです。 |
| 世界遺産パムッカレ 2011-2月撮影 | 世界遺産パムッカレ |
 「パムッカレ」とはトルコ語で「綿の宮殿」という意味です。 かつて、この地域が綿花の一大生産地だったことに由来しています。 |
 斜面全体が棚田になっているのかと思ったら違っていて 棚田になっているのはほんの一部なのです。 石灰棚の表面は細かな凸凹が刻まれています。 |
| 世界遺産パムッカレ 2011年2月撮影 | 世界遺産パムッカレ |
 マーブル(marble)という名詞はラテン語のmarmaros=白く光る石という 言葉が発祥ですが、現在のトルコ共和国のマルマラ海に 浮かぶ「マルマラ島」に由来します。 その島で約2千年前に大理石の加工が始まったと言われています。 トルコの大地には地球上の大理石の40%が眠っていると言われて いますがトルコが本格的に大理石を 採石し始めたのは1980年代になってからです。 2002年の採石量は世界第7位になりました。 それでもこの量はトルコの全埋蔵量の1%にしか過ぎません。 |
 「綿の宮殿」という名前のパムッカレですが、触ってみると 綿菓子には程遠く、コーティングされた歯のように固かったです。 岩石だから当然ですが、見た目はマシュマロのようです。 |
| トルコ・大理石(マーブル)の鉱山 | トルコ・パムッカレ |
 紀元前2世紀の終わり頃、ベルガモン(ベルガマ)の王により 建てられた古代都市の遺跡です。 多くの寺院や宗教建造物が建てられたため、 「神聖なる都市」という意味のヒエラポリスと名付けられました。 (一説に、王の妻のヒエラの名前に由来する) |
 その後、西暦2世紀から3世紀にかけて ローマ帝国の温泉保養地として利用されました。 ヘレニズム様式の柱を持つ門から約1kmに及ぶ主道路、泉、アポロ神殿、 またネクロポリスと呼ばれる アナトリア最大で1200以上の墓が建つ共同墓地等があります。 |
| トルコ・ヒエラポリス大劇場 | トルコ・ヒエラポリス大劇場 |
 イスラム教の一派で音楽と踊りによって神と一体化することを 目指すメブラーナ教。 1925年にアタチュルクの命令によって教団は解散し、 教団の創始者メブラーナの霊廟・僧院・修行地だった建物は 現在は博物館となっています。 博物館の内部にはメブラーナの棺や遺品、 マホメットのあごひげ等が展示されています。 |
 メブラーナ博物館はコンヤ市内の中央部にあります。 メブラーナ教の踊りは円錐形の帽子とクルクル回るにつれて丸く広がる スカートのような衣装が特徴。年に一回だけコンヤのスタジアムで 踊りの儀式を見ることができます。 |
| メブラーナ博物館 | トルコ・コンヤ市内 |
 キャラバンサライとは10世紀頃にトルコに建てられた隊商宿のことです。 隊を組んで長い旅を続けてきた商人達(キャラバン)にとって、 周辺に何も無い所に建てられた宿は宮殿(サライ)のように 大きく立派な建物に見えたことから キャラバンサライと呼ばれるようになりました。 現在トルコには、約100のキャラバンサライが残っていますが、 その殆どが廃墟化しています。 しかし、保存状態が良く見学可能なものもあり、 カッパドキア地方のアウズカラハン・スルタンハン・カラタイハン などが有名です。 |
 |
| アウズカラハン隊商隊の宿(キャラバンサライ) | アウズカラハン隊商隊の宿の門 |